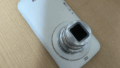初学者なりに考えてみました
障害福祉サービス事業所を開業した場合、避けて通れないのは苦情対応ではないでしょうか。
利用者本人、あるいはそのご家族から事業所にあるいは第三者委員などの機関に申し立てがあるかもしれません。対応に問題があれば指定権者である都道府県等や厚生労働省に苦情が申し立てられる可能性もあります。
方法はいくつかあると思います。
無視する
気の弱い方ですとそれで終わりかもしれません。また、苦情の中には聞いてくれればいいというお話もあります。事業所として真摯にお話を聞いて、回答は留保する的な無視であればある意味効果はあるかもしれません。
ただ、「何日までに回答や対応を教えてほしい」的な苦情対しては時間稼ぎにしかすぎず逆効果です。私は無視してうまくいったという話は聞いたことがありません。
戦う
事業所が炎上する可能性があります。たとえ不合理な苦情であっても我々の税金から給付費をもらっている事業所は戦った場合、立場から負ける可能性があります。戦う場合でも専門家に相談の上で行ったほうがいいです。
できる範囲で対応する
これが一番いい方法とは思います。利用者からの要求に必ずしも応じる必要はなく、制度はどうなっているのかを確認し、制度趣旨がわかるように回答する必要があります。
「食事をキャンセルしたのに食事提供体制加算が請求されている」とか、「半日しか利用していないのに訓練給付費が全額請求されている」など、特に給付費に関する苦情では行政に考え方を確認することが大事ではないかと思います。(食事提供は準備段階に入っているため、当日朝キャンセルしても加算の取得が可能ですが、その旨を重要事項説明書に記載することが必要です。訓練給付費は1日を単位として算定されますので、時間により増減はありません。ただし生活介護などは時間により算定単価が変わります。厚生労働省がどのようなことを報酬の評価の対象としているかを考えてみる必要があります。)また、工賃の考え方なども指定権者により認識が違うことがありますので必ず確認が必要です。
その場合、担当者の名前を必ず聞いて、メモを作りましょう。
もっとも、行政側の担当者さんって、福祉専門職として採用された職員でも、高齢から生活保護まで幅広く異動していくものですし、事務職側でも3年から5年の短いスパンの中で異動しています。前職場がインフラ(上下水道だったり建設関係だったり)だったり税金だったりそれぞれなので、必ずしも全部知っているわけではないのです。その場合担当間で確認したり場合によっては厚生労働省に問い合わせしたりしているので、時間的に余裕も必要です。
担当者を確認し、メモを作成しておくことは、後々苦情が指定権者に届いた場合、「これこれこういう内容で誰々さんに話を聞いて、このような対応を取らせていただいた。」と説明することが大事です。
指定権者でもいずれか一方のみのお話を聞いて、では運営指導にとはならないはずです。
以上初心者の私が、思い当たるところをつらつらと書いてみました。