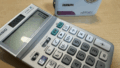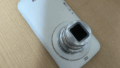就労継続支援B型_困ったときどこに相談できるのか
障害福祉サービス、例えば就労継続支援とか生活介護とかを利用中に疑問に思ったことや、対支援員との関係、工賃に関する疑問などがあった場合、どのように相談すればいいのか、初学者としての知識で記載しようと思います。
契約書や重要事項説明書にはどのように書かれているか
サービスを利用する場合、必ず利用契約が必要となります。事業所には①運営規定②利用契約書③重要事項説明書、の3点が備えられています。
①の運営規定は営業時間や契約対象者、事業地域などが記載され、虐待防止や非常時の対応などがありますが、指定機関への体制の届け出時に必要なもので、ひな形が公表されており、いずれの事業所も似たり寄ったりです。
②利用契約書には契約期間や利用料金に関する規定や契約期間、解除の条件が記載されています。ここに書いてある以外の理由で事業所から一方的に「契約解除ですので、もう来ないでください」とは言えないわけです。
③の重要事項説明書には費用の徴収や虐待防止に加え、利用者が直接苦情を申し立てられる「第三者機関」が記載されています。これは厚生労働省「社会福祉事業の経営者による福祉サービスに関する苦情解決の仕組みの指針について」で第三者委員を置くことが定められています。
この重要事項説明者は利用者が見やすい場所に掲示あるいは閲覧可能な状態にしておく必要があります。
まー③であっても実際行政側が第三者委員を決めるのではなく、事業者側が他施設の管理者とか近くの蕎麦屋のおじさんとか、利害関係さえなければ決めていいので、飲み屋のおやじに「うち第三者委員がいなくなったからやってよ」と言ってとしても資質の有無は判断できませんが、否定されるものではないので、「苦情解決を円滑・円満に図ることができる者であること。世間からの信頼性を有する者であること」であればいいのではないでしょうか。実際に第三者委員が正しく置かれているか確認されるのは運営指導で重要事項の確認が入ったときでしょうから、設置がされていない事業所もあり得ます。
事業者以外での苦情申し立て先について
苦情の種類にもよりますが、事業所を所管する指定権者には電話等で申し立てができるようです。この場合、内容によって虐待関係の窓口になったり、運営指導等の指導が必要であれば指導窓口が担当になります。虐待の場合には、支給決定を行った市町村も窓口になりえます。
相談を受けた指定権者は、指導の必要の有無を考え、対応を行うと思います。
じゃあ苦情って何なのか
では、苦情の内容は何なのでしょうか。B型事業所にありそうな話で、
・工賃が安い
→これは、事業所の働きが悪いのです。事業所は生産活動を積極的に開拓しなくてはいけません。1個0.5円単価の作業をいっぱいやることも、就労能力開発のためにはいいかもしれませんが、工賃という対価を得て、就業する意欲に結びつけるためにはほかにも仕事を見つけなくてはいけないのではないでしょうか。そのためにB型事業所には「目標工賃達成指導員加算」という制度があり、通常の人員とは別に目標工賃達成指導員を配置することで、報酬を高くできる制度もあります。
なお、ひと月の1人当たり工賃は3000円を下回ることができません。そもそもそれ以下の場合には、事業所の運営に問題がある可能性があります。
・ほかの人と1日当たりの工賃に差がある。AさんがBさんのほうがいっぱいもらっていると苦情を申し立てる
→B型事業所の場合、個々の利用者の能力により工賃に差を設けることはできません。ただし出来高や従事する生産活動により変動を設けることは絶対ダメではありません。
・支援員がえこひいきする
→支援員のカバーできる範囲にもよりますが、障害特性に合わせて支援したはずが、えこひいきととらえられる可能性もあります。
・勝手に工賃から経費が引かれている
→B型事業所では工賃から昼食代などの経費を差し引くことができません。また、余暇活動の費用も工賃からは引けません。別途徴収が必要です。
・支援員による虐待がある
→虐待には身体的なものや精神的なものなどありますが、工賃を渡さないなども経済的虐待にあたる場合もあります。
いずれの場合でも、B型事業所には「工賃規程」の制定が義務付けられており、利用者はいつでも閲覧できるはずです。もし疑問に思う場合は規程の写しをもらい、指定権者に問い合わせるとよいのではないでしょうか。
苦情申し立ての結果は
扱いが合理的なものか不適切なものかはそれこそケースごとだと思いますので、やはり何か疑問があれば第三者委員か指定権者に問い合わせるのがいいと思います。