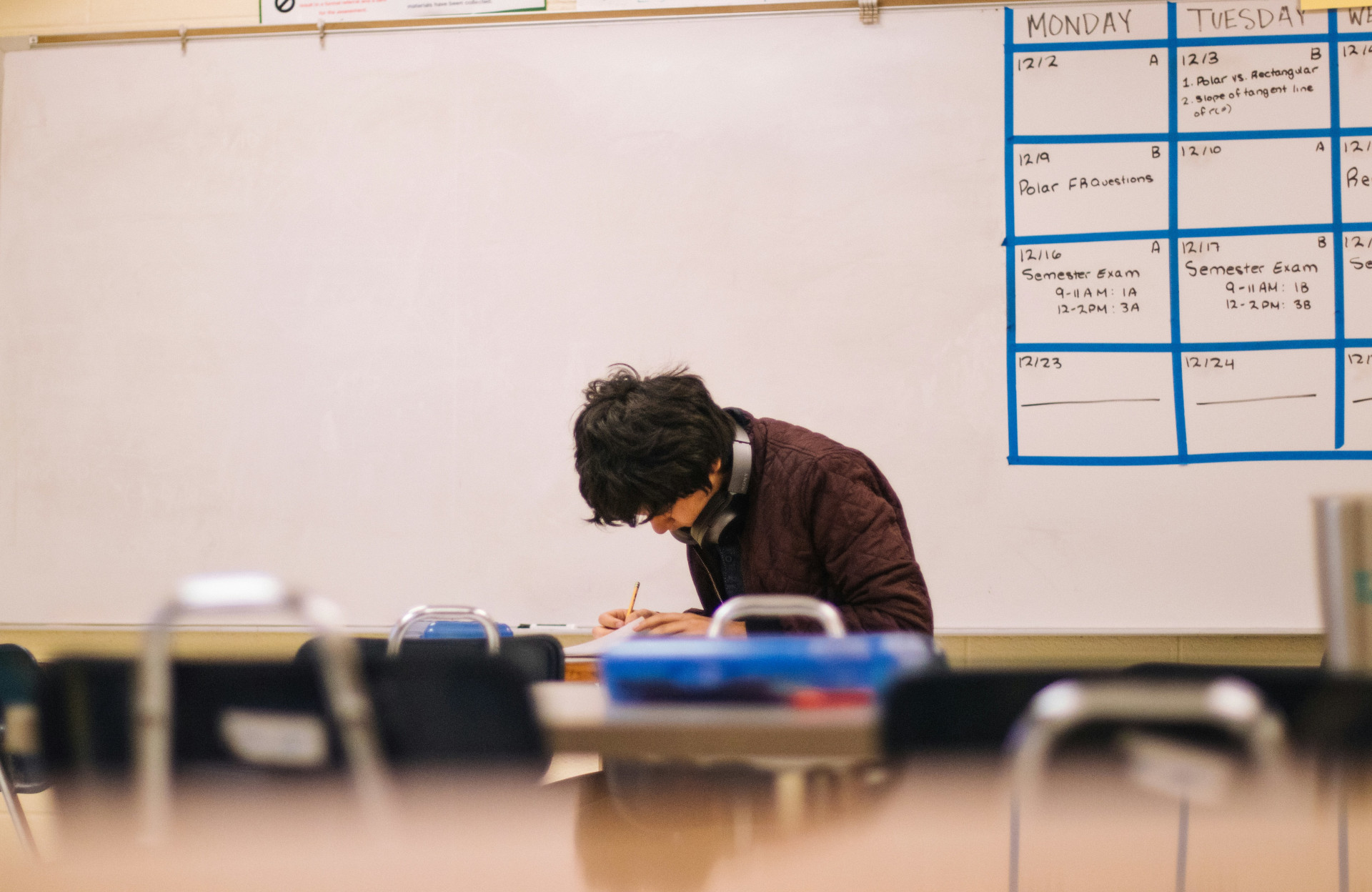原則の日数とは何
負担上限額
放課後デイサービスの受給者証を受け取ると、利用者は長男君なのに受給者は親である私になっていました。18歳以下の障害児通所受給者証の場合、「負担上限月額」は親の所得により判定されます。
ちなみに18歳になった高校3年生の時は誕生日を挟んで2枚の受給者証になりました。18歳になると受給者氏名も長男君になりました。でも所得判定は親の所得のままです。
そもそも放課後デイを含む障害福祉サービスはかかった費用の1割が自己負担となるようですが、所得によって上限が決められています。
ちなみにうちは共働きであったため、一番上の「37,200円」となっていました。この辺は応能(支払い能力に応じた請求)と応益(利用回数により額が変わる)の原則になっているようです。ただし複数のサービスを使ったり曜日ごとに違う事業所を使う場合でも上限は変わらないように、複数使う場合には上限管理事業所が指定されます。また、兄弟とも利用する場合には自治体によって負担軽減措置があるようです。
支給量とはなに?
長男君の高校生の時の受給者証の支給量欄には週1回の通所であったので、「10日/月」と記載されています。確か小学校のころは毎日利用していたので、「原則の日数」と記載されていたと思います。
原則の日数というのは、最初なんだかわからなかったのですが、「月の合計日数から土日分8日を引いた日数」ということみたいです。毎月30日や31日など違いがあるので、31日から8を引いた23日が基準になり、月により減じられるもののようです。
長男君は小学校から放課後デイまでは送迎を利用していたので、「移動支援」という項目にも同じ日数の記載がありました。幸い、長男君は小学校の高学年から一人で通所していました。